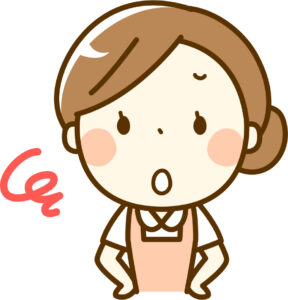
社会福祉士試験の難易度と合格率について調べてみました。社会福祉士試験は難しい試験だと言われますが、例年の合格率ってどうなっているのでしょうか?試験合格のためのモチベーション維持などについても書いています
目次
社会福祉士試験の難易度、合格率
社会福祉士は国家資格、合格すれば仕事の幅も広がりますし、介護職からステップアップすることが出来ます。
実際、介護職として日々業務を行いながら試験勉強をし、資格取得を目指している方も多いと思います。
介護業界は資格を取得することで年収が上がります。
今後のキャリアアップ、専門性のある仕事として社会福祉士をお考えになっている方も多いのではないでしょうか。
まず、社会福祉士試験の例年の合格率を見てみましょう。
その後、資格を取得するメリット、モチベーションの維持、社会福祉士の職場についてもまとめています。
社会福祉士の資格について

社会福祉士の資格は、福祉分野で唯一の国家資格です。
名称独占資格となります。
医師、看護師、弁護士などのような「業務独占資格」ではありません。
社会福祉士以外でも業務を行うことはできますが、社会福祉士試験に合格した人でなければ、社会福祉士と名乗ることができません。
社会福祉士の仕事は様々な社会福祉サービスと、困っている方を結びつけること。
活躍の場は、福祉施設、高齢者施設、学校、病院、自治体など多岐に渡ります。
社会福祉士試験の難易度、合格率
社会福祉士試験の難易度、合格率についてこの5年の数字をご紹介します。
受験者数:35,287人
合格者数:10,333人
合格率:29.3%
■第32回社会福祉士国家試験(2020年)
受験者数:39,629人
合格者数:11,612人
合格率:29.3%
■第31回社会福祉士国家試験(2019年)
受験者数:41,639人
合格者数:12,456人
合格率:29.9%
■第30回社会福祉士国家試験(2018年)
受験者数:43,937人
合格者数:13,288人
合格率:30.2%
■第29回社会福祉士国家試験(2017年)
受験者数:45,849人
合格者数:11,828人
合格率:25.8%
といった合格率となっています。
社会福祉士試験の合格率の推移
この数年は合格率30%前後で推移している状況です。
受験者数は年々減ってきていますね。
40代、50代で資格取得されている方も多い資格です。
それを考えると、年齢にあまり関係なく資格取得を目指せる資格ですから、40代で介護職に転職された方も、キャリアアップの一つとして目指してみてはいかがでしょうか。
「介護福祉士」と「精神保健福祉士」のどれを目指すかで迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
社会福祉士の職場には、
- 病院のソーシャルワーカー
- 児童相談所の児童福祉司
- 障害者施設の相談員
- 老人ホームなどの生活相談員
などがあります。
資格を取得した後の働き方も含めて、検討されてみてはと思います。
社会福祉士の難易度が高い(合格率が低い)理由
社会福祉士の資格の合格率は例年30%前後です。
過去には合格率18%台といったこともありましたが、近年は30%前後の合格率となっています。
社会福祉士試験の難易度が高い理由としては、次のようなことが挙げられます。
社会福祉士試験の難易度が高い理由/試験の出題範囲が広い
社会福祉士の資格試験は出題範囲が広いことが特徴です。
社会福祉士試験の出題範囲、19科目(18科目群)あります。
勉強しなければならない範囲が広いことが、合格率が低い一番の理由といえるでしょう。
合格するためには、満遍なく学習をすることが必要です。
しかし、これだけ広い範囲となると、どうしてもカバーしきれない苦手な科目も出てしまうでしょう。
それにせっかく覚えたとしても、時間が経つと忘れてしまうものです。
繰り返し学習をして記憶に定着させることが必要です。
しかしそれを行うにしても範囲が広く、大変です。
そしてトータルで合格点に達する必要があるため、苦手科目をいかに作らないかがポイントになってきます。
さらに、社会福祉士試験ではすべての科目で得点を取る必要があります。
これらのために社会福祉士試験の難易度が高い、と言われる理由となっています。
社会福祉士の指定科目
社会福祉士の指定科目は以下となります。
(平成21年4月1日以降)
2 現代社会と福祉
3 社会調査の基礎
4 相談援助の基盤と専門職
5 相談援助の理論と方法
6 地域福祉の理論と方法
7 福祉行財政と福祉計画
8 福祉サービスの組織と経営
9 社会保障
10 高齢者に対する支援と介護保険制度
11 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
12 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度
13 低所得者に対する支援と生活保護制度
14 保健医療サービス
15 就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度 のうち1科目
16 相談援助演習
17 相談援助実習指導
18 相談援助実習
このように範囲が広く、勉強が大変なことが難易度が高い理由となっています。
社会福祉士試験の難易度が高い理由/勉強時間が足りない
社会福祉士試験は前述したように、科目が多いことが特徴です。
福祉系資格の中では最も科目数が多い試験です。
全ての科目で得点を取ることも、合格の条件となります。
勉強時間の確保が大変で・・・といった方も多いのではないでしょうか。
仕事をしながら勉強している方だと、時間を捻出するのも大変ですよね。
残業があって勉強できない日もあるかもしれません。
社会福祉士試験に合格するには、300時間の勉強時間が必要、とも言われます。
学生であればこの勉強時間を確保しやすいかもしれませんが、介護職として働きながら、といったことだと大変です。
出題範囲が広いため、学習の手が回らないこともあるでしょう。
働きながら試験を受ける方も多いでしょうから、勉強時間が不足して合格ラインまで達しない方も多いかもしれません。
継続してコツコツと試験勉強を続けることが合格のためのポイントとなります。
社会福祉士試験の難易度が高い理由/モチベーションを維持するのが難しい
社会福祉士試験の学習は範囲が広く、長期でコツコツと勉強をすることが必要です。
社会福祉士試験の合格には300時間が目安と言われますが、それ以上に勉強時間が必要かもしれません。
平日は毎日1時間、週末や休日は5時間以上の勉強時間を確保する、などで試験までにどれくらい勉強できるか、逆算してスケジュールを立てることがまず必要でしょう。
しかし4ヵ月、5か月と学習計画を立ててみると、モチベーションが維持できるか不安・・・といった方も多いと思います。
長く勉強を続けていく場合、モチベーションを維持するのは大変です。
仕事が忙しかったり、予定通りに進まないことも多いと思います。
社会福祉士試験に合格するためには、モチベーションをいかに維持し、勉強の際の集中力を高めることも重要となります。
社会福祉士試験の合格基準が厳しい
社会福祉士試験には合格ラインがあります。
以下の2つを満たす必要があります。
- 問題の総得点の60%程度を基準に、問題の難易度で補正した点数以上の得点
- 18科目全てで得点する(1点以上得点する)
総得点の60%程度を基準、とあるように問題の難易度によって、合格ラインが変動するようです。
確実に合格するには、60%以上を得点する必要があります。
また、社会福祉士試験に合格するには一度の試験で全科目に合格する必要があります。
つまり総得点で合格ラインを超えていても、1科目でも0点があると不合格となってしまいます。
社会福祉士 実務試験 パートの扱いは?
社会福祉士試験の受験資格を満たすには、養成学校や福祉系高校を卒業するルートがあります。
ほか、介護業務で3年以上(従業期間1,095日、従業日数540日以上)の経験を積む「実務経験ルート」があります。
介護の仕事をしている方は、実務経験ルートを選ぶことになるかと思います。
介護の現場でパート、アルバイトとして勤務されている方もいらっしゃると思います。
実務経験として、パートやアルバイトとしての勤務でも、条件を満たせばOKとなります。
社会福祉士を取得するための費用
社会福祉士になるには、社会福祉士の国家試験を受けなくてはなりません。
試験の受験資格が設けられています。
受験資格を得るには、福祉系の4年制大学や短大などに進学をして卒業する必要があります。
4年制の大学に進学する場合には、入学から卒業まで400万円前後かかることになります。
短大の場合には、200万円前後の費用がかかります。
専門学校の場合は150万円前後です。
通信制で学ぶ場合には、80万円前後という費用がかかります。
いずれも選ぶ学校・通信教育によって費用には差があります。
通信制の場合は、費用を安く抑えることができるメリットがありますが、一人で勉強を継続しなければならず、モチベーションを維持するのが大変、というデメリットもあります。
社会福祉士を取得するまでに必要な勉強時間
社会福祉士試験に合格するためにどれくらの勉強時間が必要なのでしょうか?
約300時間、と言われています。
もちろん、人によっては300時間以上の勉強時間が必要でしょう。
効率よく勉強できるのであれば、それ以下でもいいのかもしれません。
仕事をしながら社会福祉士試験を受ける方は、隙間時間を利用して勉強を行ったり、計画を立てて学習を進めていく必要があるでしょう。
試験日から逆算をして、スケジュールを立てることが大切になります。
どのくらいの学習ペースで進めていけばいいか、把握することが必要です。
苦手科目はしっかりと対策を立てなくてはなりません。
1科目でも0点があると、総合的に合格ラインを超えていても不合格となります。
社会福祉士の試験は、1年に1回となります。
後から後悔しないように、しっかりと計画立てて勉強を進めていく必要があります。
社会福祉士試験の難易度、合格率 まとめ
社会福祉士試験についてご紹介しました。
社会福祉士試験の難易度は福祉系試験では高く、合格率も低いといえます。
しかし、資格を取得することで働き方の選択肢は確実に広がることになります。
介護職からキャリアアップしたい、とお考えの方も多いと思います。
相談員として働きたい、児童相談所で児童福祉司として働きたい、など目標をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
3人に1人しか合格できないと考えるか、3人に1人も合格できると考えるか。
長丁場の勉強期間となりますから、モチベーションをしっかりと維持して対策を行っていきましょう。
