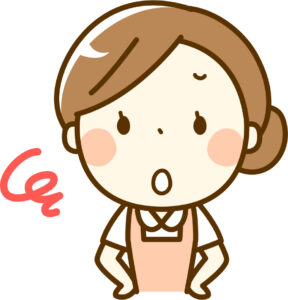
目次
介護職のシフトが不公平な理由、解決方法
介護職員として働く際、勤務スケジュール、すなわちシフトは極めて重要な要素です。
シフトの作成においては公平性が求められますが、時折、不公平に感じるシフトになってしまうことがあります。これは、介護業界における一般的な問題とも言えるでしょう。
シフト作成者(リーダー)が自分自身の都合に合わせたシフトになっているのではないか? あるいは、特定のスタッフを優遇したシフトになっているのではないか? と感じることがあります。
不公平なシフトにより、勤務が困難に感じられる場合や、過度に厳しいシフトになってしまっている場合、どのような対策を取れば良いのでしょうか。
介護職員として、不公平に感じるシフトや過酷なシフトに直面した際の解決策について、以下で詳しく解説します。この情報は、介護職員だけでなく、介護業界に関心を持つ全ての人々にとっても役に立つ知識となると思います。
介護職のシフト:なぜ不公平性が生じるのか?

介護職のシフトは不公平?その原因と解決策。
不満を抱える介護職員の声など、多く見たり聞いたりします。
介護職員として働いていると、シフトに不公平感を感じることがありませんか?
シフト作成は介護施設の運営に欠かせない重要な業務ですが、介護職員の数や希望が多様であればあるほど、シフトを組むのは難しくなります。
正社員は夜勤が必須であったり、パートさんは家庭の事情などで出勤できる日が限られていたり、施設によっては独自のルールや事情があったりします。
そうしたシフト作成の条件が複雑になればなるほど、シフト作成者も大変ですし、スタッフの要望を反映したシフトを作ることも困難になります。
シフトが決まっても、急な休みや変更の要望があって…とシフト作成者は常に頭を悩ませています。
しかし、一方で介護職員としても不公平なシフトだと働く気力も失われますし、モチベーションも低下します。
では、どうして介護職の不公平なシフトが生まれてしまうのか、その原因を見てみましょう。
介護職員不足
まず、最大の原因は介護職員不足です。
介護職員が足りなければ、どうしてもキツイシフトになってしまいますし、正循環シフト(日勤→夜勤→休み)も実現できません。
キツイシフトが続けば、離職率も高くなりますし、介護施設は負のスパイラルに陥ってしまいます。
そんな職場からは早く逃げ出した方が良いかもしれませんね。
休暇や出勤希望の偏り
次に、スタッフの休暇や出勤希望が偏っていることも原因です。
スタッフの中には、家庭や学業などで休みが必要だったり、出勤できる日が決まっていたりします。
そうした希望を優先してシフトに反映させると、他のスタッフの休暇や出勤日も偏ってしまいます。
希望を無視すれば辞められてしまうかもしれませんし、人手不足の現状ではそれも避けたいですよね。
でも、休暇や出勤が偏っていると他のスタッフも不満になりますし、負担も大きくなります。
人間関係のバランスやスタッフの能力
さらに、シフトに入るスタッフの能力や人間関係のバランスも重要です。
介護施設では、一人夜勤を除いて、複数の介護職員が協力して介護にあたります。
特に入浴や食事などの時間帯は、介護職員の人数を多く配置する必要があります。
しかし、シフトに入るスタッフの能力差が大きい場合(新人ばかりやベテランばかりなど)や、人間関係が悪い場合(仲の良い人と一緒になりたいなど)は、負担が偏ったり、ストレスが溜まったりします。
人員配置上、バランスよくシフトに入ることが難しいこともありますが、続くと不公平感や不満が高まります。
シフト区分が多い
また、介護施設によっては勤務区分が非常に多くなっており、シフトを組むのが複雑です。
日勤だけでも5つや6つの勤務区分があったり、夜勤も複数の勤務区分があったりすると、どうシフトを組むかで頭を悩ませます。
そもそも介護職員の出勤事情から勤務区分が増えるケースが多いと思いますが、増えすぎるとシフト作成者も大変ですし、シフト作成が困難になります。
シフト作成者のスキルが不足している
最後に、シフト作成者のスキル不足も原因です。
介護施設のシフト作成をするためには、シフト作成者が現場のことをよく理解している必要があります。
リーダーになったばかりだったり、他部署から異動してきたばかりだったりすると、スキル不足で介護職員が納得できるシフトを作れないこともあります。
ブラック介護施設の見分け方と転職のススメ
介護士として働く上で気をつけたいポイントがあります。
介護士は高齢者や障害者の生活を支える大切な仕事ですが、その一方で、
「シフトがきつい」
という悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
シフトがきついだけならまだしも、勤務先の介護施設がブラック企業と呼ばれるような環境であれば、仕事に行きたくないと思う気持ちもわかります。
ブラック介護施設とは、どのような特徴を持つ施設なのでしょうか。
そして、ブラック介護施設から脱出するためには、どのように転職すれば良いのでしょうか。
この記事では、ブラック介護施設の見分け方と転職のススメについてお伝えします。
ブラック介護施設の特徴
ブラック介護施設とは、労働環境や待遇が悪く、介護士の負担が大きい施設のことです。
ブラック介護施設には、以下のような特徴があります。
過度な長時間労働
介護職は体力的にも精神的にも負担が大きい仕事です。
適切な休息が取れない状況が続くと、健康を害するだけでなく、介護の質も低下します。
労働時間が法定を超えている、または残業が多い施設は注意が必要です。
休日が取れない
週休二日制が守られていない、または有給休暇が取りにくい施設も問題です。
休日が確保されていないと、職員の健康やモチベーションに影響を及ぼします。
給料が安い、低賃金
介護職は専門的な知識と技術を必要とする仕事です。
その労働に見合った適切な賃金が支払われていない場合、それはブラック企業の可能性があります。
また、賃金が低いと生活を維持するのが難しくなり、職員のモチベーションを下げる可能性があります。
パワハラ・モラハラ
上司や同僚からのパワハラやモラハラが存在する場合、その職場環境は健全とは言えません。
職員の精神的な健康を害し、介護の質を低下させる可能性があります。
高い離職率
高い離職率は職場環境の問題を示している可能性があります。
特に、新人がすぐに辞めてしまう場合、研修体制や人間関係、労働条件などに問題がある可能性があります。
適切な研修がない
新人や未経験者に対する適切な研修や教育がない場合、それはブラック企業の可能性があります。
適切な研修がないと、職員のスキルアップが難しく、介護の質が低下する可能性があります。
人手不足
人手不足が常態化している施設は、過重労働やサービスの質の低下を引き起こす可能性があります。
また、人手不足は職員一人一人の負担を増やし、ミスや事故のリスクを高める可能性もあります。
安全対策が不十分
介護施設では、職員と利用者の両方の安全が確保されていることが重要です。
例えば、施設内の清潔さ、感染症対策、防災設備、職員の体調管理など、安全対策が不十分な施設は避けるべきです。
不適切な労働条件
労働契約が曖昧であったり、労働条件が不適切であったりする場合、それはブラック企業の可能性があります。
例えば、労働時間や休日、賃金、福利厚生などが明確に示されていない、または法律に適合していない場合などです。
コミュニケーション不足
上層部と現場スタッフ間、またはスタッフ同士のコミュニケーションが不足している場合、それは問題がある可能性を示しています。
コミュニケーション不足は、職場の雰囲気を悪化させ、職員のモチベーションを下げる可能性があります。
また、問題が起きたときに適切に対応できない可能性もあります。
ブラック介護施設から転職する方法
もしブラック介護施設に就職や転職をしてしまった、という場合。
ブラック介護施設とは
ブラック介護施設とは、過酷な労働条件や人間関係、低い給与などで働く介護職員の心身を病ませる施設のことです。
ブラック介護施設に勤めていると、ストレスや疲労が溜まり、やりがいやモチベーションが失われてしまいます。
そんな状況から抜け出したいと思っている方は多いでしょう。
しかし、ブラック介護施設から転職するのは簡単ではありません。
自分で求人を探すのは時間や労力がかかりますし、自分に合った施設を見つけるのは難しいです。
また、ブラック介護施設に長く勤めていると、自信や自己評価が低くなり、自分の能力や価値を正しく伝えられなくなってしまいます。
そこで、ブラック介護施設から転職するために転職エージェントを利用することをおすすめします。
転職エージェントを利用して働きやすい介護施設へ転職する
転職エージェントとは、介護職員の転職をサポートする専門のコンサルタントのことです。
転職エージェントに登録すると、以下のようなメリットがあります。
- 豊富な求人情報を紹介してもらえる
- 自分に合った施設や条件を提案してもらえる
- 履歴書や面接のアドバイスを受けられる
- 交渉や手続きの代行をしてもらえる
転職エージェントは、介護業界の動向や市場価値を知っているプロです。
自分では見つけられないような良い求人や条件を紹介してくれます。
また、自分の強みや魅力を引き出してくれます。
転職エージェントに相談することで、ブラック介護施設から脱出し、より良い環境で働くことができるようになります。
ブラック介護施設から転職するためには、まずは転職エージェントに登録することが大切です。
登録は無料で簡単にできますし、気軽に相談できます。
ブラック介護施設に悩んでいる方は、ぜひ一度転職エージェントに相談してみてください。
介護職の不公平なシフトとは
介護職のシフト制とその問題点について。
介護職は、デイサービスなどの一部を除いて、ほとんどの場合シフト制で働く仕事です。
シフト制のメリットは、自分の都合に合わせて働けることや、体力的に無理がないように調整できることです。
しかし、実際には人手不足や他のスタッフの休暇の影響で、理想的なシフトが組めないことも多いでしょう。
たまになら我慢できても、不公平や過酷なシフトが続くと、介護職のモチベーションや健康に悪影響を及ぼします。
具体的には、以下のようなシフトが不公平や過酷だと感じるかもしれません。
- 他のスタッフと比べて休日が少ないシフト
- 夜勤や早朝勤務が連続するシフト
- 遅番から早番への切り替えが多いシフト
- 遅番や夜勤が偏って多いシフト
- 夜勤が少なくて収入が減るシフト
- 自分の希望や能力を無視したシフト
- 休日が前半や後半に集中するシフト
などです。
介護施設によっては、人手不足のせいで、夜明け早番や、夜明け夜明け日勤という過酷なシフトを強いられることもあります。
5連勤、6連勤もあるかもしれません。
シフトに公平性が欠けている場合も問題です。
例えば、一部のスタッフだけが常に夜勤や休日勤務を担当させられる一方で、他のスタッフはそういった負担の大きいシフトをほとんど担当しない、という状況です。
介護職のシフト不公平がもたらす深刻な影響
介護職は、高齢者や障害者の生活を支える重要な仕事ですが、シフトに不公平を感じることで様々な問題が起こります。
シフト不公平とは、一部の職員が夜勤や休日勤務などの負担の大きいシフトを多く担当する一方で、他の職員はそういったシフトをほとんど担当しないといった状況です。
また、シフトが不規則であったり、シフトの変更が頻繁に行われると、職員の生活リズムが乱れることもシフト不公平の一つです。
介護職のシフト不公平は、次のような影響を及ぼします。
職員のストレスとモチベーション低下
シフト不公平によって介護職は自分の予定が上手くこなせなくなりますし、自分だけ辛いシフトになっている…と感じることで、ストレスを抱えモチベーション低下につながります。
ストレスやモチベーション低下は、職場の雰囲気や人間関係にも悪影響を与えます。
介護サービスの質への悪影響
シフト不公平によるストレスやモチベーション低下は、介護サービスの質にも影響します。
介護サービスの質が低下すると、利用者さんや入居者さんに対する配慮や気遣いが欠けたり、ミスや事故が起こりやすくなったりします。
これは、利用者さんや入居者さんの満足度や安全性を低下させるだけでなく、介護施設の評判や経営にもマイナスの影響を与えます。
介護職員の離職率の上昇
シフト不公平は、介護職員の離職率を上げる要因ともなります。
これらのシフト条件は、介護職員の体調不良や病気、家庭やプライベートの問題などにも影響します。
また、シフト不公平に耐えられなくなり、異動や転職・退職を考える人も増えます。
これは、介護業界の人手不足や離職率の上昇につながります。
介護職の不公平なシフト問題と解決策
介護職にとって、シフトは仕事のやりがいや生活の質に大きく影響します。
しかし、介護職のシフトは、施設や事業所によって様々で、一般的にはシフト希望制度が採用されています。
シフト希望制度とは、介護職員が自分の希望する休日や勤務時間を申請し、それをもとにシフト作成者が勤務表を作成する制度です。
この制度は、介護職員の自由度や柔軟性を高めるメリットがありますが、不十分な場合、職員のライフスタイルや個々の事情が考慮されず、不公平なシフトが生じる可能性があります。
不公平なシフトは、職場の雰囲気や職員の満足度を低下させるだけでなく、介護の質や安全性にも影響します。
そこで、シフト希望制度を改善し、職員一人ひとりの希望や事情を尊重することが必要です。
具体的には、以下のような方法が有効です。
シフトの作成過程を透明化する
シフト作成者は、介護職員の希望を反映した勤務表案を作成し、それを介護職員全体に公開します。
その後、介護職員は、勤務表案に対して意見や要望を出します。
そして、シフト作成者は、それらをもとに勤務表案を修正します。
このようにして、最終的な勤務表が決定されます。
この方法は、シフト作成者と介護職員がコミュニケーションを取り合い、互いの理解と信頼を深める効果があります。
注意点としては、声が大きな職員の希望が優先されやすくなるということがあります。
シフト作成ルールを制定する
シフト作成者は、利用者や施設のニーズと介護職員の希望とのバランスをとることに苦労します。
そのため、ルールをしっかり制定することが必要になります。
例えば、
- 希望休の日数や提出期限
- 連休や土日祝日の取得条件
- 連続勤務日数の上限
などをルールを明確にしておきましょう。
そうすることで、シフト作成者がシフト作成に取り掛かりやすくなります。
シフト管理ツールの活用
シフト管理ツールを活用することで、シフトの作成や管理を効率化し、公平性を確保することが可能になります。
シフト管理ツールは、以下のような機能を備えています。
- シフト希望の入力や確認
- シフト作成の自動化や最適化
- シフトの変更や連絡
- シフトの即時変更、可視化
シフト管理ツールを使うことで、シフト作成者の負担を軽減し、介護職員の不公平感や不満を減らすことができます。
職員同士の協力
職員同士でコミュニケーションを取り、互いの希望や事情を理解し合うことも重要です。
また、必要に応じてシフトを調整し合うことで、職場全体としての公平性を確保することができます。
例えば、
- 休みが重なっている場合、交代してもらう
- 勤務時間が長い場合、代わりに仕事を引き受ける
- 突発的な用事がある場合、代理で勤務する
などの協力を行うことで、シフトに柔軟に対応することができます。
異動や転職・退職を検討する
シフトの問題が解決しない場合、異動や転職・退職を検討することも一つの手段です。
異動先で新たな環境とシフトを経験することで、問題を解決することが可能になる場合があります。
配属先が変わればシフトも変わります。
リーダーや管理者の考え方も変わりますから、シフト作成の仕組み自体も変わるのです。
転職・退職する
転職・退職する場合は、より良い労働環境を整えて人材を確保しようという動きも見られる介護業界において、自分に合った介護施設を探すことができます。
介護施設の数は増え続けており、より良いシフト環境を得ることができる可能性も高まっています。
その場合、記事中でもご紹介しましたが、
などを利用して情報収集される方法がおすすめです。
介護職 不公平なシフト まとめ
介護職として働き続けていく上では、シフトの公平性はとても重要です。
不公平なシフトは、想像以上にストレスが溜まるものです。
あなただけではなく、他の職員や利用者にも影響します。
そこで、シフト希望制度を改善し、職員一人ひとりの希望や事情を尊重することが必要です。
また、異動や転職・退職を検討することも一つの手段です。
介護職は仕事内容だけでなく、シフトも自分に合ったもので働くことが長く勤務するポイントでもあります。
ぜひ自分らしく働ける職場をお探しになってみていただきたいと思います。
